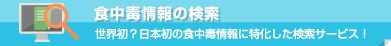食品衛生のプロ、ミスター0がゆく!
札幌O-157による集団食中毒の感染メカニズムについて
札幌で漬物(白菜の浅漬け)による腸管出血性大腸菌O(オー)157の集団食中毒が発生しましたが、どうして生肉でない食材から腸管出血性大腸菌O(オー)157が発症するのか?・・・という疑問が浮かぶのではないでしょうか。
確かに今回の食中毒事件では、特定された原因食材が漬物(白菜の浅漬け)であり、その具材には一切生肉等は使われていないようです。
しかし、食中毒というものは、すべて「原因食材を直接食べて起こる」とは限らないのです。
例えば、腸管出血性大腸菌O(オー)157に感染している食肉をたべて人(保菌者)が、重度の食中毒症状ではなく、軽い下痢症状だけに留まった症状の場合、普段通りの生活をすることが多々あります。
その場合、体内には、腸管出血性大腸菌O(オー)157の細菌が残っている状態ですから、特に用便後の手洗いがしっかりとできていない場合には、手指に微量の腸管出血性大腸菌O(オー)157が付着したままになることがあります。
もし、手洗い不足の状態のままで食材に触れ調理作業を行ったとすると、腸管出血性大腸菌O(オー)157が調理した食材に付着することがあるのです。これを二次感染(交差汚染)と言います。
今回の食中毒事件では、このような二次感染(食品⇒人⇒食品)のルートで腸管出血性大腸菌O(オー)157が集団感染したのではないかと思います。(あくまで推測の域を超えませんが・・・。)
手洗いは、衛生管理の基本です。食中毒の予防対策で最も重要で簡単な衛生的な行為です。
特に、食品の調理作業を行う方たちは、日々の健康管理に気をつけ、万一、下痢・腹痛・吐き気などの症状がある場合には、医師の診断を受け、調理作業を休む勇気を持ってください。
たった一人の管理不足が集団感染を引き起こすこともあるのです。
また、食品工場や飲食店等で食品の調理を担当している方々は、定期的な検便検査を実施し、保菌状態をチェックするように心がけてください。